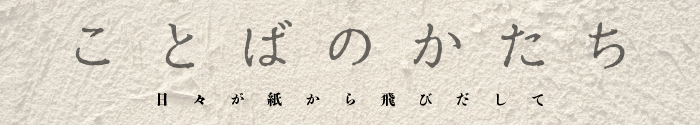POETRY FOR YOU 2
「空港からバスに乗ったよ」と片手で母にメールを打つ。顔を上げると、高速バスの窓から大きな虹が見えた。雲を突き抜けた虹は、ゆるやかな弧を描き、滑走路のあたりに着地している。きれいなアーチ型だ。星印のジェット機が、広い秋空を斜めに突っ切っていく。ジェット機の乗客たちは、自分たちが虹をくぐったことを知っているだろうか。カメラモードのiPhoneを窓に向けながら、「まるで観光客だ」と気恥ずかしく思う。「北海道の空が広い」なんて、敢えて意識したくはなかった。
年末年始を含め、年に三度は札幌に帰る。仕事相手には「ずいぶん頻繁ですね」と言われるが、その理由をうまく答えられない。帰省には、明確な目的がない。儀式のような重さもない。単なる「習慣」なのだ。東京の生活は「目的」だけでできている。絡まった糸屑のような路線図の中で、「快速」の「快」の字が赤くただれている。
知り合いの詩人が三人、偶然にも、私の帰省と同時期に北海道を訪れていた。その一人が福間さんだ。「札幌の穴場があれば教えて欲しい」とメールが飛んできた。
札幌の「穴場」はどこだろう。遠足前に駆け込んだ埃っぽい駄菓子屋か。スプレーの落書きの痕が残る中学校の校門か。部活の先輩とサーティワンを食べたイオンのフードコートか。スリッパと板チョコで客をもてなす古本屋か。これは「穴場」というより、うっかり落ちてしまった「穴」の話かもしれない。
札幌での高校時代は、裏通りのおしゃれな雑貨屋や喫茶店を喜々として巡った。けれど東京で暮らす今、札幌の店が模している「東京」に、むず痒さを覚える。札幌の街を歩いていると、しばしば「正しい東京」の答え合わせをしている心地がする。「ここにしかない」と思っていた多くのものが、「東京」の模造品だった。
二十四歳の今、札幌では極力「ダサい」ことしかしたくない。町で唯一のコンビニでチューハイを買う。両親と回転寿司に行く。ジャージ姿でたむろす中学生に生温かい視線を送る。酔った女友達と手を繋いで北大通りを歩く。鞄から反射的にカメラは出るが、詩人の名刺は出てこない。
寝る前、枕の上にiPhoneを置き、国会前のネット中継を観た。デモの怒号は規則的な韻を踏み、そのリズムに合わせてプラカードが躍る。そこに立っていたかもしれない自分を想像して、指先でウィンドウを閉じる。アヒルの人形が置かれた実家の寝室に、秋の沈黙がおりる。
中学時代の友人は、「行きつけ」のティールームに案内してくれた。小花柄のテーブルクロスを見つめながら、味のぼやけたハーブティーをすする。「彼氏の会社がブラック」とか「すすきののライブハウスでナンパされて」などの雑多な話題に耳を傾ける。一年前も似た話を聞いたように思うが、私のやる気のない相槌にもおそらく変化はない。
「うちらも年食った」とか「老けたくない」などとぼやきつつ、特に対策を講じることなく、私たちは時間に負けていく。旅立たない私たちは安定している。ミルクパフェを、小花柄を、新色のリップグロスを健やかに消費していく。故郷の穴ぐらの中で、愛しい過去をささやき合っている。