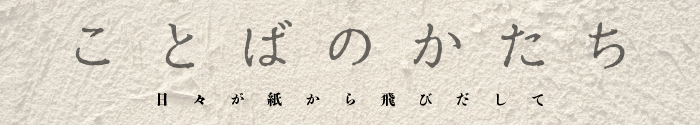POETRY FOR YOU 2
なんの悩みもないように広がる風景のなかに、突然、戦争の記憶をよみがえらせる窪みがあらわれる。何を言おう。第一次世界大戦と第二次世界大戦。冬を生き抜いた母たちのイメージが、人がつながってつくる糸で刺繍した春の谷間に踊った。いまは春ではないが、土と草を踏んで、ぼくは新しい汗をかいた。それから、ひとりごと。胸のうちを通る小さな花にあいさつする。夜になっても泣かないために。八月、濡れた砂も思い出だけの抵抗もオールドファッションだ。リンドウのような秋の花まで咲いて。昼間、いくら気温があがっても、朝晩は涼しい。だから、かな。泉の冷たい水を味わった妻が言う。もう少し歩きたい。あと三十分くらい。ぼくはここに来てからずっと気分がいい。東京ではガクガクしていた膝がしゃんとして、よく眠れて、呼吸がラクだ。フヴァーラ。ありがとう。そうだ、ぼくは日に日に進歩する。わずかずつでも、いろんなことから自由になっている。朔太郎とか中也とか光太郎とか、生意気な中学生にしか思えない。ここでは通じない冗談が目の奥に走る。リルケがなんとかという傑作を書いた町に行ってみませんか。いいえ、けっこうです。それよりもおいしいワインの醸造所に連れていってください。事実よりも、内面的なもの、感情的なものの優位を前提とする後期印象派の、さまざまの染みへの、異議申し立てを考える。たとえば、こうである。彼と彼女、ミティアとナターリアは、ぼくが去年の十二月にわが団塊の世代の文学について講演した首都リュブリャナの大学で出会った。ともに二十一歳。あるとき、二人は、同じ日、同じ病院で生まれたことを知った。ミティアの母クセーニャは、そのノーヴォメストの病院で女の子を産んだ女性と自分がまちがえられそうになったことをおぼえている。その女性はコルパ川流域の小さな村から来ていた。この夏、ナターリアは、その村の近くの、宿泊施設もある川べりの食堂で働いている。クセーニャと彼女の夫ボヤンと妻とぼくはそこでおいしいマスを食べた。ナターリアともちょっと話した。クセーニャとボヤンも、ナターリアに会うのは初めてだった。そういう事実の耳を舐める妖怪の舌からどう逃れたらいいのか。ノック、ノック、天国のドアをノックしろ。ボブ・ディランの懐かしい歌がきこえてくる。中学生のとき、この歌が大好きだった。クセーニャが言った。ワインで酔ったぼくは、スロヴェニア語の本の並ぶ青い棚の前に立つ。スロヴェニアの青いには賢いという意味がある。ボヤンがそう説明した。本の並ぶ青い棚、つまり賢い棚なのである。ノック、ノック、天国のドアをノックしろ。ぼくが最終目的地だと思ってきた青い家は、ここで賢い家になった。たどりつくのは先のことだが、ものすごく先というわけではない。ぼくはミティアとナターリアの三倍も歩いちゃったのだ。若い二人の前には長い道のりがある。クセーニャが心配そうに言った。彼女は賢い。旅で訪れた場所から種を持って帰っっていろんな木を育てている。デザートのロールケーキと格闘しながら妻が言う。賢い人。スロヴェニアの青い母たちのひとりだ。妻は想像した。ミティアとナターリアはきっと青い糸で結ばれている。日本人の好きな赤い糸の物語の修正版だ。運命だけじゃない。人の注意と努力が作用して、赤が青になる。さあ、歩こう。そしてノックしよう。妻は、毎晩、徐々にはっきりと見えてくる空の星座に感激している。ぼくたちの泊まった部屋は、ドアの鍵の操作がむずかしかった。妻が困っているとナターリアが来てドアをあけてくれた。