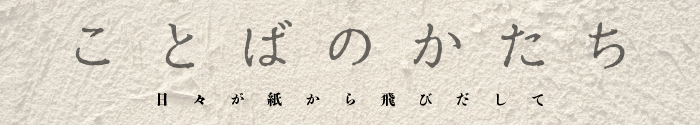冬はつとめて
富田昭一は現在八十六歳。一人暮らしをしている。彼には年子の姉と、四つ上の姉がいた。年子の姉とは子供の頃には喧嘩もしたが、何せ男の子一人だったから、両親にも二人の姉にもかわいがられて育った。終戦後、父親の友人が再開した小さな食品加工会社に住み込みで働くようになってからも、週末には社長が持たせてくれる油揚げを提げ、一週間分の洗濯物を抱え、必ず実家に帰る。家族に、あんたにしてはよく続いてるわよね、昭ちゃんとこの油揚げは黄色くっておいしいわ、などと褒められて、月曜日に実家から出勤する。すぐ上の姉のほうは、無事に結婚したが、長女のほうは戦争で婚期を逃し、実家にいながら勤めに出ていた。彼も結婚はしなかった。家族や会社のひとたちが見合いの話を持ってきてくれたこともあったが、見合いのあとには実家の炬燵にもぐりこんで、「やっぱり、僕は姉さんたちというるほうが気楽でいいや」などと言うものだから、姉さんたちもまんざらではなくて、話はすぐに流れてしまった。一人身の気楽さから大した貯金もせずに彼が定年退職したころには、実家には上の姉さん一人だったから、彼はアパートを引き払っていっしょに暮した。姉さんの貯金は、両親の病気のときに半分に減っていたけれど、それでも年金はあるし、二人合わせればなんとでもなるようで二人で温泉に行ってみたり、函館の夜景を見たり、パリにも行った。姉さんは習い事にも熱心で、絵画教室、お花の教室、短歌の教室へと忙しく出かけていた。「昭ちゃんも、なんか始めたらいい」と勧められるのだが、彼は姉さんに付き合うだけだった。姉さんは八十過ぎても元気だった。ところが、四年前、姉さんは敷居のところに躓いて、骨折し、入院したきり、急激に弱って、亡くなった。古くなった家の畳は沈んで、段差ができていた。彼はずっと後悔している。「バリアフリーにしときゃあ、よかったんだよな、そしたら、姉さんは死なずにすんだ」、と、未だ修繕していない敷居のところに来ては、思う。「富田さん、どう、元気?」と、民生委員の田村さんが訪ねてくれる。田村さんは、情報通でいろいろ教えてくれる。「富田さん、あそこの、交差点のセブンイレブンあったとこあるでしょ、」
「え、あそこ、つぶれたの」
「そうよ、暮れだったかなあ、つぶれちゃって、ずっと空いてたんだけどね、こないだ餃子屋ができてさ、けっこう人、入ってるのよ。行ってみたらいいよ」
「おいしいの?」
「わたしはまだ入ってないけど、家内がおいしいって」
「ああ、そう、じゃあ行ってみるわ。ありがとう。」彼は素直に言って、その日の夜には行くのだ。田村さんは彼にしてみれば、子供くらいの歳であるが、富田昭一はすっかり頼っている。「なんか困ってることない?」と聞かれて、「あ、そうそう、これなんだけどね」とフライパンを持ってきて、「ここがさあ、もう穴開きそうなの」と見せる。姉が亡くなってからというもの、彼は自炊している。野菜や卵で炒め物をつくるのだが、火を強くするので、あっという間に底を焦がしてしまう。物持ちはいい富田昭一だったが、姉がずっと使ってきたフライパンは、もはや鉄だか焦げだかすっかり見分けがつかない。「あーこれは、だめだな、」田村さんも言った。
「こういうの、どこで買えばいいのかなあ、確か学校のほうに金物屋があったと思ってね、こないだ行ってみたんだけど、もうずいぶん前につぶれちゃったんだな、確か。困っちゃって」
田村さんは、あー、と考えて「ホームセンターで買えるんじゃないかなあ、国道の向こうにできたでしょ、ああ、でもちょっと遠いかなあ、いいよ、おれ、今度ついであるとき、買ってきてあげるよ」
そう言われて、彼は「いいよ、いいよ」と遠慮した。
彼は少しわくわくしている。用事が出来るのはうれしいことだ。今日は餃子の店、明日はホームセンター、今夜はフライパンを使わずにすむし、うまい具合だ。田村さんが来てくれると、事が好転する。
前夜、おいしい餃子を食べた彼は、
今日は、朝からホームセンターに出かける。
平日の午前のだだっ広いホームセンターを感心しながら歩くが、フライパンがどこにあるのか、わからない。ずいぶん歩いた。ようやく見つけた鍋の棚に、親しんできた鉄のフライパンがないので、お店の人に聞いて、一番安い二千円のテフロン加工のフライパンを買った。帰りには国道から一本左の筋を通って帰る。先へ行くと桜並木があるのだ。桜の花は三分咲き。咲きかけの桜の下を、新しいフライパンを持って歩く気分は悪くない。悪くないなあ、と、疲れてベンチに腰掛けた彼は、ニコニコしながら通る人を見やる。母親と小さな女の子が通る。薄曇りの乏しい桜の下を黄色い雨傘かかげて女の子が歩いてゆくのを、彼は大ニコニコになって見送る。
夜、あぐらをかきながら「鶴瓶の家族に乾杯」を見る。登場した小学生たちが可笑しくて、彼はまた、笑った。笑ったあと、ちょっと照れた彼は身体を逸らして、遺影の姉さんを見る。
2015.3.28