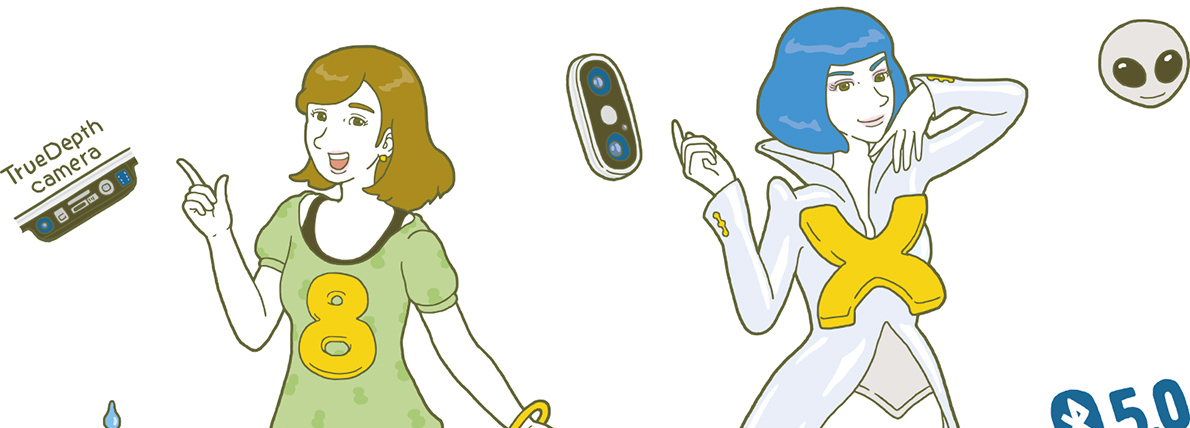2017.11.06
成功した企業ゆえの悩み
iPhone Xは、あらゆる意味で、これからのiPhone、ひいては今後のスマートフォンの方向性を示唆している製品です。
筆者も含めて、iPhone 6~8のプラスモデルを使ったことのある人ならば、見やすく情報量の多い大型スクリーンのメリットを実感しているでしょう。一方で、よりコンパクトな標準モデルのホールドの良さも捨てがたいところがあります。
iPhone Xは、上下左右のベゼル幅を極限まで狭めることで、プラスモデルを上回るスクリーンサイズを誇りながら、筐体サイズはiPhone 8よりわずかに大きいレベルに留めており、いわば両者の良いところをバランスよく融合することに成功したのです。
しかも、ピクセル密度が458ppiと歴代最高の緻密さを持つスーパーレティナHDディスプレイなので、発色と滑らかさの点でも群を抜く美しさを実現。一方で、タッチIDに代わる個人認証技術として組み込まれたフェイスIDは、指紋を利用するよりもはるかに安全で欺くことが難しい本人確認を可能としています。
また、Qi規格に準拠したワイヤレス充電機能はもちろん、2眼式のメインカメラを利用するプロ並みのポートレートライティング撮影機能はiPhone 8プラスと同様に備えており、ニューラルエンジンを内蔵するA11バイオニックチップによって可能となる高速処理や顔認識やアニ文字のための機械学習能力と併せて、現在考えうる最上の仕様が凝縮されているといえるのです。
実のところ、ここ数年に渡ってアップルは、成功した企業ゆえの悩みを抱えていました。それはiPhoneという超人気製品に対する膨大な需要を満たしながら、毎年のように新たな技術を投入して先進性をアピールしなくてはならないというジレンマです。
同一カテゴリ内で最高の製品を作るというポリシーを掲げたアップルにとって、可能な限り最新かつ最良の技術を採用したいのはやまやまなのですが、そのような技術は量産が難しかったり、コストが高すぎたりします。そうなると、ひと頃に比べて落ち着いたとはいえ、四半期ごとに5000万台以上販売されているiPhoneの中心的なモデルに組み込むことは難しいといわざるをえません。
たとえば、LCDに比べて歩留まりが悪かったOLEDを一部のアンドロイドスマートフォンが先行して採用できた大きな理由は、製造すべき台数がiPhoneと比べて少なくて済むためでした。
ところが、単に水準以上の製品を出しているだけでは、期待感の高いユーザやメディアから良い評価を得られないのがアップルの宿命です。iPhone誕生の10周年にあたる今年は、特にそのプレッシャーが強まっていました。
そこでアップルが採ったのは、量産性とコストバランスに優れたiPhone 8/8プラスと、現時点では製造とコスト面で不利になっても最先端技術を搭載したiPhone Xを同時に発表するという戦略でした。
実際にもiPhone Xの製造台数は、フェイスIDユニットの歩留まりが影響して週あたり40万台といわれており、四半期ベースでもわずか480万台しか生産できない計算です(それでも市販の電子機器としては十分に多いともいえますが…)。したがって、大量生産向きのiPhone 8/8プラスと、未来へのビジョンを見せられるiPhone Xを併売することは理に叶っているわけです。
もちろん、アップルとしてはiPhone Xの量産とコスト問題の解決が間に合えば、こちらをiPhone 7/ 7プラスの直接的な後継機としたかったと思われます。それが今年は難しかったわけですが、来年以降は確実にそれを実行に移してくるでしょう。
その際には、現行のプラスモデルのように画面サイズのために筐体を大型化する必要性が薄れるので、主力モデルのサイズを再び一本化することも考えられます。あるいは、今の標準モデルと同等の画面サイズながら、よりコンパクトな筐体を持つ“iPhoneミニ”的な製品展開すらありうるかもしれません。いずれにしても、iPhone Xには、これからのiPhoneの方向性を示す原型としての役割があるのです。