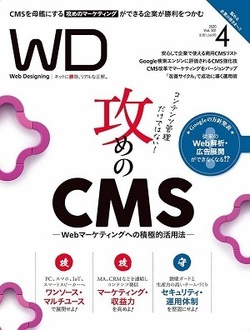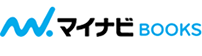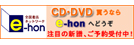2020.03.13
一億総編集者計画 Web Designing 2020年4月号
ビジネスマンのファシリテーション力 チームをまとめる統率力の応用
【今回のお悩み】「代理店、制作陣、マーケター、イベンターなど、複数のプロが集まるプロジェクトを取りまとめるディレクターなのですが、クリエィティブ担保をはじめ成果にコミットできる一枚岩のチーム編成を組むのに苦労しています…」
Illustration: 浦野周平・児玉潤一
関係者に力を発揮してもらえる環境づくり
計画(1)相手の業務は徹底的に理解しよう
今回は、プロジェクトチームをまとめるための「ファシリテーション力」を探ります。職種の異なる人、専門家や作家といった個性の強い人たちと仕事をすることが多い編集者から、そのポイントは学べそうです。
まず、ご機嫌を取るような仲ではなく、尊敬し合う関係を築くには何が大事なのか考えていきましょう。第一に「あなたが求めていること」を相手と共有できていることが肝心です。「なぜ私に頼んだの?」と相手に思わせてしまえば、モチベーションは下がってしまいます。「あなただからこそ、お願いしたい!」と依頼できるかが重要です。
そのためには、職務内容や得意な部分を理解しておく必要があります。例えば、デザイン業務においても、「資料を読む」「ラフを描く」「素材をつくる」「配色、配置する」などのプロセスが存在します。
細かい部分までは難しいとはいえ、プロセスの数や大枠の内容は把握しておきましょう。そのプロセスがプロジェクトにおいてどんな役割を担い、どんな表現が可能かまで考えることができれば理想的です。
計画(2)関係者ネットワークを構築しよう
外部のパートナーや取材先など、さまざまな人と関わり、制作において「依頼すること」が多い編集者も、前述した相手目線のマインドセットが自ずと求められる仕事です。ただ、1対1での向き合い方も重要ですが、複数人を含む関係性構築の意識も大切になってきます。
編集者には、ライター、カメラマン、スタイリスト、ヘアメイク、モデル、広告代理店、クライアント、取材対象者などの多種多様な人々と関わるシーンがあります。関係者との会議で気を遣いすぎたり、現場で撮れ高を担保する重圧と戦ったり、アドリブが求められるような状況が多かったり、常に緊張感が付きまとう仕事です。大勢の人が関わり、費用と時間もかけながら仕事をする以上、仕方がないことだと思います。
ここで言いたいのは、大勢の人と関わりながら仕事に取り組む編集者が、関係者全員とのネットワークを大事にする意識を持っているということです。コミュニケーションにプレッシャーを感じず、むしろ次のビジネスを生み出すような関係網を意識的に築いているように感じられます。
これは、目の前のプロジェクトに留まらない視野であり、「また、仕事をするかも」「別のプロジェクトにも参加してもらいたい」といった言動にもつながります。関係者にとって何が有益かを理解することが前提となるため、結局は相手の理解が必須です。各専門家の力を見出し、ビジネスとして成立させる役割を担っている編集者の姿勢からは、長期的な関係性構築も見据えた、チームとの付き合い方が学べます。
ビジネスにおいては、単一プロジェクトの成功だけでなく、その先の広がりや継続性を考えることも重要です。ネットワーク構築は、お悩みのような問題の解決だけでなく、より本質的なビジネスの課題解決につながります。
チームを率いるリーダーとしての行動指針
計画(3)人を動かせる説明力を養おう
前半は「メンバーとの関わり方」に注目しました。ここからは、「プロジェクトを取りまとめる人物には何ができるか?」「どういったスキルが必要か?」「どういうマインドでいるべきか?」などを中心に述べていきます。
では早速ですが、プロジェクトを遂行する上での「中心人物」とはどういった人でしょうか? いろいろな定義があるとは思いますが、ここでは「ファシリテーション力がある人」を中心人物とします。言い換えると、「うまく説明して納得させる力がある人」です。
「ファシリテーション」の言葉の意味は割愛しますが、制作工程における各関係者との相互理解、意見をまとめる合意形成、現場の空気づくりから仕切りまで長けている人が「ファシリテーション力がある人」だと考えています。いわゆるリーダーシップがある人でもありますが、ポイントは「人を動かす説明力」があるかというところです。
「説明する」という行為は、編集力の基本です。企画を通すにも、取材対象者に出演してもらうにも、有能なスタッフに参加してもらうにも、すべて説明が必要です。そして何よりも読者(消費者)に対して説明ができないと媒体も情報も認めてもらえません。情感的な言動を客観的な事情に基づいて話せることが「説明」なのです。
例えば、説明もなくおすすめされたお店に「行きたい」とは思わないはずです。料理の名前や価格、店名といった情報だけ説明されても行こうとは思えません。お店に入った経緯や、食べた感想などの「情感的な言動」を説明してもらわないと、わざわざ足を運びたくはならないといったところです。
自身の言葉や経験により説明責任を果たせる人こそが中心人物です。説明をして納得をしてもらうプレゼン力は磨いておきたいものですね。
計画(4)課題を発掘できるリーダーになろう
編集作業では、現場進行や予算管理など、担当編集者が決裁権を持つことが多いです。キャスティング、打ち合わせをいつ・どこでするか、撮影の際の昼食を何にするか、事細かく決めることになります。
事業責任や経営責任という文脈ではなく、「物事をうまく運ぶ」という視点では、編集者の仕事とお悩みにあるディレクターの役割はクロスオーバーします。
いずれも大事なのは、自分の考えや意見を持つことです。相手のことを考えすぎてしまい、自身の考えを持たずプロジェクトに参加するのは命取り。前半で相手を理解する重要性を説きましたが、ベースには「あなたの志向」が必要です。そして、その考えや意見をディレクターとしてメンバーに共有することが欠かせません。
したがって、意見を持ってプロジェクトメンバーをまとめて率いる「統率力」がディレクターには必要となってきます。ディレクターの職務責任が多岐に及び、二の足を踏んでしまいそうですが、心持ちひとつで変わるはずです。
最後に、ディレクターがどういったマインドを持つべきか考えてみようと思います。これからの時代を生き抜く思考や行動様式をまとめた山口周氏の著書※には、「課題解決よりも課題発掘を心がける」と書かれていました。
今回のお悩みでも、「一枚岩のチーム編成を組む」という部分への対応に目が行きがちですが、そもそも問題が起きないようにする、危機察知能力にも似た課題発掘も必要だと思います。顕在化された課題への対応だけでなく、「問題点を見つける」視野も持ち、ポジティブなアラートを出せるリーダーを目指したいですね。
※「ニュータイプの時代 新時代を生き抜く24の思考・行動様式」(ダイヤモンド社刊)

- 教えてくれたのは…酒井新悟
- RIDE MEDIA&DESIGN株式会社 代表取締役社長 https://www.rmd.co.jp/ Facebook ID Shingo Sakai 大学卒業後、祥伝社へ入社。編集者としてファッション誌「Boon」に携わった後、BoonのWeb版「boon.web」でWebディレクターとして活躍。2006年にWeb、メディア、デザインを総合的に制作及びディレクションをするRIDE MEDIA&DESIGN株式会社を設立。現在は、従来の職域にとらわれない新しい時代の「編集力」を活かして、様々なソリューションビジネスに携わっている。