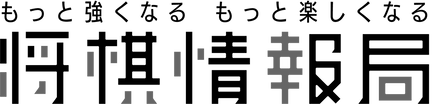2024.12.26
将棋戦略「配置理論」講座 ~新用語一覧~
将棋界に突如現れた「配置理論」。他分野のアイデアをヒントに、独自の理論を構築しています。新用語も多く使われていますので、まとめてみました!
限定記事や限定動画など特典が盛り沢山!将棋情報局ゴールドメンバーご入会はこちらから
皆さんこんにちは。
本記事では、将棋の最善手を導き出すための新しい理論、「配置理論」をご紹介します。
詳しくは、2024年12月24日に発売の『配置理論で学ぶ 将棋戦略思考』(著:ゆに@将棋戦略)にも載っていますので、チェックしてみてくださいね。
※本稿は、ゆに@将棋戦略著『配置理論で学ぶ 将棋戦略思考』の内容をもとに編集部が再構成したものです。
第1回講座:概論&駒の働きの基本成分
このように定義したとき、形勢判断の諸要素はいずれも駒の働きによって説明される。すなわち、「駒の損得」は駒の働きの総量に、「玉の安全度」は守りの働きに関連しており、また「手番」は駒の働きを高める権利と見做すことが出来る。
一般に、その駒が相手玉に近ければ近いほど攻めの働きが大きくなる性質があるが、厳密には「境界効果」や「弱いマス」の影響も考慮する必要がある。
一般に、その駒が自玉に近ければ近いほど守りの働きが大きくなる性質があるが、厳密には「境界効果」や「弱いマス」の影響も考慮する必要がある。
これらのような影響を持つ駒は、たとえ攻めや守りの働きが乏しくても、「働いている」と見做される。
第2回講座:9×9の境界が駒の働きに与える影響

左辺から攻められた場合は金銀が働くため、左辺は安全スペース

右辺から攻められると金銀が働かないため、右辺は危険スペース
第3回講座:「弱いマス」とマスの偶奇性

第4回講座:第4回:駒の働きと自由な手番
以上が、配置理論の駒の働きと自由な手番についての講座です。
詳しくは、2024年12月24日に発売の『配置理論で学ぶ 将棋戦略思考』(著:ゆに@将棋戦略)に載っています。
本書ではほかにも、「駒の働きの不確定性」などの新たな概念を用い、駒の働きの言語化に挑んでいます。これまでの講座の内容をもとに、結論を導き出していますので、ぜひ読んでください。
限定記事や限定動画など特典が盛り沢山!将棋情報局ゴールドメンバーご入会はこちらから
「配置理論」講座一覧
第1回:概論&駒の働きの基本成分
第2回:9×9の境界が駒の働きに与える影響
第3回:「弱いマス」とマスの偶奇性
第4回:駒の働きと自由な手番
番外編:配置理論用語一覧(今読んでいる記事)
第1回:概論&駒の働きの基本成分
第2回:9×9の境界が駒の働きに与える影響
第3回:「弱いマス」とマスの偶奇性
第4回:駒の働きと自由な手番
番外編:配置理論用語一覧(今読んでいる記事)
皆さんこんにちは。
本記事では、将棋の最善手を導き出すための新しい理論、「配置理論」をご紹介します。
詳しくは、2024年12月24日に発売の『配置理論で学ぶ 将棋戦略思考』(著:ゆに@将棋戦略)にも載っていますので、チェックしてみてくださいね。
※本稿は、ゆに@将棋戦略著『配置理論で学ぶ 将棋戦略思考』の内容をもとに編集部が再構成したものです。
本記事の目次
0 新用語一覧
1 第1回講座で登場した用語
1-1 駒の働き
1-2 攻めの働き
1-3 守りの働き
1-4 第3の働き
1-5 駒の働きの位置依存性
2 第2回講座で登場した用語
2-1 並進操作
2-2 並進不変性
2-3 境界近傍
2-4 境界効果
2-5 射線管理
2-6 安全スペース
2-7 危険スペース
3 第3回講座で登場した用語
3-1 弱いマス
3-2 アクセシビリティ
3-3 上下非対称性
3-4 偶奇非対称性
3-5 偶奇バランス
3-6 偶奇表示
4 第4回講座で登場した用語
4-1 自由な手番
4-2 駒の働きの潜在性と顕在性
5 配置理論を体系的に学ぶならこの本がおすすめ
0 新用語一覧
1 第1回講座で登場した用語
1-1 駒の働き
1-2 攻めの働き
1-3 守りの働き
1-4 第3の働き
1-5 駒の働きの位置依存性
2 第2回講座で登場した用語
2-1 並進操作
2-2 並進不変性
2-3 境界近傍
2-4 境界効果
2-5 射線管理
2-6 安全スペース
2-7 危険スペース
3 第3回講座で登場した用語
3-1 弱いマス
3-2 アクセシビリティ
3-3 上下非対称性
3-4 偶奇非対称性
3-5 偶奇バランス
3-6 偶奇表示
4 第4回講座で登場した用語
4-1 自由な手番
4-2 駒の働きの潜在性と顕在性
5 配置理論を体系的に学ぶならこの本がおすすめ
新用語一覧
本記事では、第1回講座~第4回講座で登場した用語をまとめています。第1回講座で登場した用語
ここでは、第1回講座中で登場した用語を紹介しています。第1回講座:概論&駒の働きの基本成分
駒の働き
従来的な解釈によれば、駒の働きは形勢判断の一要素であり、駒の位置に関連した概念である。本講座においては、「将棋ゲームの目的達成に対する、一つ一つの駒の寄与」と定義することにする。このように定義したとき、形勢判断の諸要素はいずれも駒の働きによって説明される。すなわち、「駒の損得」は駒の働きの総量に、「玉の安全度」は守りの働きに関連しており、また「手番」は駒の働きを高める権利と見做すことが出来る。
攻めの働き
駒の働きの構成要素の一つで、相手玉によって規定される。攻めの働きの大きさは、その駒と相手玉との位置関係によって決まる。一般に、その駒が相手玉に近ければ近いほど攻めの働きが大きくなる性質があるが、厳密には「境界効果」や「弱いマス」の影響も考慮する必要がある。
守りの働き
駒の働きの構成要素の一つで、自玉によって規定される。守りの働きの大きさは、その駒と自玉との位置関係によって決まる。一般に、その駒が自玉に近ければ近いほど守りの働きが大きくなる性質があるが、厳密には「境界効果」や「弱いマス」の影響も考慮する必要がある。
第3の働き
駒の働きの構成要素の一つで、その駒が存在すること、そのものによって生じる働き。第3の働きが盤上に及ぼす影響は様々あるが、代表的なものとして、相手の持ち駒の打ち込みの妨害、相手の大駒の利きの妨害などがある。これらのような影響を持つ駒は、たとえ攻めや守りの働きが乏しくても、「働いている」と見做される。
駒の働きの位置依存性
駒の働きがその駒の位置に依存して変化するという、将棋の性質。また、「駒の働きと駒の位置との関係」の意味でも用いる。第2回講座で登場した用語
ここでは、第2回講座中で登場した用語を紹介しています。第2回講座:9×9の境界が駒の働きに与える影響
並進操作
ある部分図について、駒の相対位置を変化させずに絶対位置のみを変化させる操作。端的に言えば、スライドである。並進不変性
ある量が並進操作に対して不変であるとき、その量は並進不変性を持つ、と表現する。ある量が並進不変性を持つということは、その量が駒の相対位置にのみ依存し、絶対位置には依存しないということに相当する。 駒の働きは将棋盤が無限に広い場合にのみ、並進不変性を持つと考えられる。一方、9×9の境界が存在する通常の将棋盤では、並進不変性は明らかに成り立たなくなる。境界近傍
文字通り、盤上における9×9の境界の傍のこと。境界の外には駒が存在できないため、盤上の境界近傍と中央近傍は異なる性質を持っている。境界効果
境界の外には駒が存在できないという性質から、玉が境界近傍に位置する時は①玉が狭くなる、②境界側からは攻められなくなる、という二つの特性が生じ、玉の周囲にいる駒(自軍の守り駒、敵軍の攻め駒)の働きが高まると考えられる。 このような場合において、境界が駒の働きに与える影響を境界効果という。射線管理
FPS用語の一つで、大体の意味は「遮蔽物を使って相手の弾に当たらないように、空間や敵の位置を意識すること」である。 将棋における射線管理では、自玉周辺の自軍の金銀を遮蔽物とみなし、敵軍の攻め駒との関係を意識する。安全スペース
ある領域から敵軍の攻め駒が接近してくることを想定する。このとき、敵軍の攻め駒に対して自軍の金銀が自玉を遮蔽しているなら、その領域は安全スペースである。図1においては左辺が安全スペースに相当する。
左辺から攻められた場合は金銀が働くため、左辺は安全スペース
危険スペース
ある領域から敵軍の攻め駒が接近してくることを想定する。このとき、敵軍の攻め駒に対して自玉が露出しているなら、その領域は危険スペースである。図1においては右辺が危険スペースに相当する。
右辺から攻められると金銀が働かないため、右辺は危険スペース
第3回講座で登場した用語
ここでは、第3回講座中で登場した用語を紹介しています。第3回講座:「弱いマス」とマスの偶奇性
弱いマス
玉以外の駒が利いていないマスを弱いマスという。自陣における弱いマスは守りの働きと関係しており、弱いマスがあると自軍の守り駒が働きづらくなる性質がある。アクセシビリティ
自陣(敵陣)に対する、敵軍(自軍)の侵入のしやすさのこと。弱いマスには駒が侵入しやすいことから、弱いマスはアクセシビリティを高める要素であると言える。上下非対称性
弱いマスを生じるメカニズムの一つで、将棋の駒における、前方への利きと後方への利きの非対称性を指す。将棋の駒の利きは左右対称である一方、後方に利く駒は少なく、上下については対称でない性質がある。偶奇非対称性
弱いマスを生じるメカニズムの一つで、将棋の駒における、偶数マスへの利きと奇数マスへの利きの非対称性を指す。偶数マスと奇数マスは以下のように定義される。 〇偶数マス:2四や6六のようにマスを示す二つの数字の和が偶数となるマス 〇奇数マス:2三や6五のようにマスを示す二つの数字の和が奇数となるマス偶奇バランス
金銀の偶奇非対称性を数値化したもので、偶数マスを+1、奇数マスを−1として、金銀の利きについてこれらを足し合わせたものを偶奇バランスと呼ぶ。自陣の偶奇バランスは基本的に、偶数or奇数マスの金or銀、下の境界に接している偶数or奇数マスの金or銀の8要素から計算できる。偶奇表示
先述した8要素の、それぞれの数を示したもの。図のように表記する。
第4回講座で登場した用語
ここでは、第4回講座中で登場した用語を紹介しています。第4回講座:第4回:駒の働きと自由な手番
自由な手番
文字通り、制約のない手番のこと。例えば駒取りや王手をかけられているときの手番には制約があり、このような場合は自由な手番ではない。 自由な手番は駒の働きに変換することができ、またその意味で駒の働きと同質であると言える。駒の働きの潜在性と顕在性
ある駒の働きについて、その将来が不確定的である性質を駒の働きの潜在性、逆に確定的である性質を駒の働きの顕在性と呼ぶ。潜在性を持つ駒を潜在的な駒、顕在性を持つ駒を顕在的な駒、とも表現する。 ある時点において十分に働いている駒は、その時点で顕在的であると言える。一方で十分に働いていない駒は、将来的により働きが高まる可能性があり、自由な手番があれば潜在的であると見做せる。配置理論を体系的に学ぶならこの本がおすすめ
ここまでお読みいただきありがとうございました!以上が、配置理論の駒の働きと自由な手番についての講座です。
詳しくは、2024年12月24日に発売の『配置理論で学ぶ 将棋戦略思考』(著:ゆに@将棋戦略)に載っています。
本書ではほかにも、「駒の働きの不確定性」などの新たな概念を用い、駒の働きの言語化に挑んでいます。これまでの講座の内容をもとに、結論を導き出していますので、ぜひ読んでください。
限定記事や限定動画など特典が盛り沢山!将棋情報局ゴールドメンバーご入会はこちらから
将棋情報局では、お得なキャンペーンや新着コンテンツの情報をお届けしています。