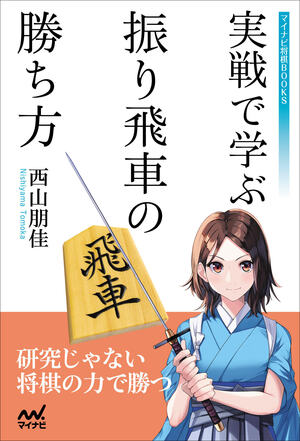2024.07.09
先手中飛車で勝つ方法は?西山朋佳女流三冠から見た「人間的な勝ちやすさ」を解説!
本記事では、"西山朋佳流"振り飛車で勝つ方法を級位者~初段の人にも分かりやすいように解説します。
振り飛車の場合は、理詰めで考えるよりも勝ちやすい形に対する感覚が大切です。
豪快な棋風で知られる西山朋佳女流三冠から見た「人間的な勝ちやすさ」を学んでいきましょう!
限定記事や限定動画など特典が盛り沢山!将棋情報局ゴールドメンバーご入会はこちらから
皆さんこんにちは。
本記事では、"西山朋佳流"振り飛車の勝ち方をご紹介します。
詳しくは、2022年8月19日に発売の『実戦で学ぶ振り飛車の勝ち方』(西山朋佳)にも載っていますので、チェックしてみてくださいね。
※本稿は、西山朋佳著『実戦で学ぶ振り飛車の勝ち方』の内容をもとに編集部が再構成したものです。
※後手三間飛車の勝ち方についてはこちらの記事で解説しています。
※相振り飛車の勝ち方についてはこちらの記事で解説しています。
私(西山)にとって中飛車は「手厚く指して勝つ戦法」です。
5筋に位を取って、中央に模様を張り、相手の仕掛けを封じます。
第1図が理想形で、まずは有利に進めやすくなります。

▲4七銀・3八金の木村美濃が中央に厚みを築くことができる陣形で、中飛車と相性がいいのです。
ただし、後手番ではこの理想形に組むまでに先手が速攻を仕掛けてくるので、△6三銀型が実現しづらくなります。
先手・後手の1手の差で展開が大きく変わってくることが多いため、私は先手での中飛車採用率が高くなっています。
また、相手が穴熊のときは別の考え方が必要になりますので、ご注意ください。
相手が急戦の場合はだいたい銀2枚を中央に繰り出して攻めてきますので、その厚みに対抗する手段がこの▲4七銀・3八金型なのです。
さて、ここからは私の実戦を題材にして解説していきましょう。
第2図は里見香奈女流王座との一戦、私が先手番の中飛車で、ここでは相手の急戦が確定しています。

皆さんもよく遭遇する局面でしょう。
ここから▲4七銀△7二飛に▲3八金(第3図)と進んで理想的な形になりました。


この直前の手が△3五歩で、△3五銀と出る手がなくなったので▲5六銀と出やすくなった意味があります。
玉の囲いが薄くなって心配になる方もいるかもしれませんが、
「玉が薄くなった」と嘆くより「中央が手厚くなった」と喜びましょう。それが中飛車の考え方です。
第4図で居飛車としては△7二飛と寄った以上、△7五歩と仕掛けたいところです。
第4図から△7五歩▲同歩△同銀▲同銀△同飛と進みます。
ここで▲6六角(第5図)が好手と覚えましょう。

第5図で飛車を逃げる場所が難しいです。
というわけで、全て優勢です。
先ほどの第3図のタイミングでも△7五歩(第6図)から銀交換できますが、この場合は△7五同飛に▲5九飛と引くか、▲6六角~▲7八飛と強く戦っても、飛車の打ち込みが後手のほうが多いため十分です。

第6図の仕掛けは後手の角が使いづらいので考えにくい順だと思います。

ここで▲7八金が西山印の一手。
中飛車では戦いの中で左金を玉にくっつけていくような指し方もあり、そんなことができたらカッコいいんですが、私はあっさり▲7八金と上がります。これでいいんです。
▲7八金は左辺の受けを考えたときは最強の手で、7七はもちろん、8八もケアしています。
特にこの局面では△1三角が無理をした形で次に▲1五歩の攻めが見えているので、▲7八金で左辺を受け止めて端から攻めるのが有利と見ました。
実戦も△7六歩▲1五歩(第8図)となって端攻めが実現しました。

銀だけでなく金も玉から離れて不安に思う方もいるかもしれませんが、私の感覚では「これで安泰」です。だって手厚いので。
もちろん横から攻められたら弱いですが、7八金がいるのでその心配はありません。
第8図から端でポイントを挙げて第9図に進みました。

途中で打った▲1二歩が手筋の垂れ歩です。▲1一歩成を見せて、この1歩で玉を危険地帯(=端)に追い込むことができます。
とにかく左辺を受け止めて端で勝とうというのがこちらの作戦ですから、これは大事な一手です。
さて、第9図がポイントの局面です。
ここで皆さんならどう指しますか?
実は数手前から狙っていた構想がありました。
浮いている香をタダで取りにいこうという手なのですが、おわかりでしょうか?

▲2六金~▲1一歩成~▲1六歩を狙っています。
最後に唯一残っていた守りの金を攻撃に使うので、良い子はマネしちゃいけない手ですが、厚みを重視する自分の棋風がよく表れています。
さすがに囲いがゼロ枚になるので相手の反撃をしっかりと読む必要があります。
△7六歩▲6五桂△7五銀▲同銀△同飛の銀交換には▲1一歩成△同玉▲2四歩(第11図)があります。
で後手陣は一気に危ない形になります。
実戦は△7六歩▲6五桂に△3三銀▲2六金△6五銀▲同銀右△3四桂▲2七金△1二玉(第12図)と桂の力で金を引かされましたが、▲3六歩と今度は桂頭に狙いを定めて攻めていきました。

以下、こちらの玉も薄いので怖いところもありましたが、勝ちきることができました。

投了図以下は△1二同玉▲1三銀成△同角▲同香成△同玉▲1四飛△同玉▲2五金△1三玉▲1四香までの詰みとなります。
本局のポイントは▲4七銀~▲5六銀と中央に厚みを築いたことで、その時点でやや作戦勝ちになっていると思います。
▲7八金は勇気のいる手ですが、左辺を受け止めてからの端攻めが見えているので、いい判断だったかと思っています。
以上が"西山朋佳流"先手中飛車の勝ち方です。
詳しくは、2022年8月19日発売の『実戦で学ぶ振り飛車の勝ち方』(西山朋佳)に載っています。
本書ではほかにも、「三間飛車」や「相振り飛車」の勝ち方も解説しています。
ぜひ本書を読んで、"西山朋佳流"振り飛車の勝ち方をマスターしてください! 限定記事や限定動画など特典が盛り沢山!将棋情報局ゴールドメンバーご入会はこちらから
本記事では、"西山朋佳流"振り飛車の勝ち方をご紹介します。
詳しくは、2022年8月19日に発売の『実戦で学ぶ振り飛車の勝ち方』(西山朋佳)にも載っていますので、チェックしてみてくださいね。
※本稿は、西山朋佳著『実戦で学ぶ振り飛車の勝ち方』の内容をもとに編集部が再構成したものです。
※後手三間飛車の勝ち方についてはこちらの記事で解説しています。
※相振り飛車の勝ち方についてはこちらの記事で解説しています。
目次
1 "西山朋佳流"先手中飛車の勝ち方
1-1 ポイント①先手中飛車は手厚く勝つ戦法
1-2 ポイント②玉の堅さよりも中央の手厚さを重視
1-3 ポイント③▲7八金は左辺を受けるときの最強手
1-4 ポイント④守備駒も攻撃に参加
2 "西山朋佳流"振り飛車の勝ち方を体系的に学ぶならこの本がおすすめ
1 "西山朋佳流"先手中飛車の勝ち方
1-1 ポイント①先手中飛車は手厚く勝つ戦法
1-2 ポイント②玉の堅さよりも中央の手厚さを重視
1-3 ポイント③▲7八金は左辺を受けるときの最強手
1-4 ポイント④守備駒も攻撃に参加
2 "西山朋佳流"振り飛車の勝ち方を体系的に学ぶならこの本がおすすめ
"西山朋佳流"先手中飛車の勝ち方
ポイント①先手中飛車は手厚く勝つ戦法
まず、中飛車とはどういう戦法でしょうか?私(西山)にとって中飛車は「手厚く指して勝つ戦法」です。
5筋に位を取って、中央に模様を張り、相手の仕掛けを封じます。
第1図が理想形で、まずは有利に進めやすくなります。

▲4七銀・3八金の木村美濃が中央に厚みを築くことができる陣形で、中飛車と相性がいいのです。
ただし、後手番ではこの理想形に組むまでに先手が速攻を仕掛けてくるので、△6三銀型が実現しづらくなります。
先手・後手の1手の差で展開が大きく変わってくることが多いため、私は先手での中飛車採用率が高くなっています。
また、相手が穴熊のときは別の考え方が必要になりますので、ご注意ください。
相手が急戦の場合はだいたい銀2枚を中央に繰り出して攻めてきますので、その厚みに対抗する手段がこの▲4七銀・3八金型なのです。
さて、ここからは私の実戦を題材にして解説していきましょう。
第2図は里見香奈女流王座との一戦、私が先手番の中飛車で、ここでは相手の急戦が確定しています。

皆さんもよく遭遇する局面でしょう。
ここから▲4七銀△7二飛に▲3八金(第3図)と進んで理想的な形になりました。

ポイント②玉の堅さよりも中央の手厚さを重視
第3図から数手進んで第4図。4七の銀を▲5六銀と上がりました。
この直前の手が△3五歩で、△3五銀と出る手がなくなったので▲5六銀と出やすくなった意味があります。
玉の囲いが薄くなって心配になる方もいるかもしれませんが、
①中央の厚みが絶大で4~6筋から相手に仕掛けられることがない。
②▲4五歩で1度出た後手の銀を引かせることが確定している。
③(この局面限定の話だが、)飛車が7二に寄っているため場合によっては▲6五銀右から銀交換して▲6一銀の割り打ちを狙う筋がある。
これらのメリットを考えると▲5六銀は上がるべきです。②▲4五歩で1度出た後手の銀を引かせることが確定している。
③(この局面限定の話だが、)飛車が7二に寄っているため場合によっては▲6五銀右から銀交換して▲6一銀の割り打ちを狙う筋がある。
「玉が薄くなった」と嘆くより「中央が手厚くなった」と喜びましょう。それが中飛車の考え方です。
第4図で居飛車としては△7二飛と寄った以上、△7五歩と仕掛けたいところです。
第4図から△7五歩▲同歩△同銀▲同銀△同飛と進みます。
ここで▲6六角(第5図)が好手と覚えましょう。

第5図で飛車を逃げる場所が難しいです。
①△7二飛は▲6一銀
②△7一飛や△7三飛は▲8二銀
③△7四飛や△7六飛なら▲6五銀~▲5四歩
②△7一飛や△7三飛は▲8二銀
③△7四飛や△7六飛なら▲6五銀~▲5四歩
というわけで、全て優勢です。
先ほどの第3図のタイミングでも△7五歩(第6図)から銀交換できますが、この場合は△7五同飛に▲5九飛と引くか、▲6六角~▲7八飛と強く戦っても、飛車の打ち込みが後手のほうが多いため十分です。

第6図の仕掛けは後手の角が使いづらいので考えにくい順だと思います。
ポイント③▲7八金は左辺を受けるときの最強手
第7図は第4図から△1三角▲6八角と進み、前述の▲6六角の筋を消してから仕掛けられたところです。
ここで▲7八金が西山印の一手。
中飛車では戦いの中で左金を玉にくっつけていくような指し方もあり、そんなことができたらカッコいいんですが、私はあっさり▲7八金と上がります。これでいいんです。
▲7八金は左辺の受けを考えたときは最強の手で、7七はもちろん、8八もケアしています。
特にこの局面では△1三角が無理をした形で次に▲1五歩の攻めが見えているので、▲7八金で左辺を受け止めて端から攻めるのが有利と見ました。
実戦も△7六歩▲1五歩(第8図)となって端攻めが実現しました。

銀だけでなく金も玉から離れて不安に思う方もいるかもしれませんが、私の感覚では「これで安泰」です。だって手厚いので。
もちろん横から攻められたら弱いですが、7八金がいるのでその心配はありません。
第8図から端でポイントを挙げて第9図に進みました。

途中で打った▲1二歩が手筋の垂れ歩です。▲1一歩成を見せて、この1歩で玉を危険地帯(=端)に追い込むことができます。
とにかく左辺を受け止めて端で勝とうというのがこちらの作戦ですから、これは大事な一手です。
さて、第9図がポイントの局面です。
ここで皆さんならどう指しますか?
実は数手前から狙っていた構想がありました。
浮いている香をタダで取りにいこうという手なのですが、おわかりでしょうか?
ポイント④守備駒も攻撃に参加
私の指した手は▲2七金(第10図)です。
▲2六金~▲1一歩成~▲1六歩を狙っています。
最後に唯一残っていた守りの金を攻撃に使うので、良い子はマネしちゃいけない手ですが、厚みを重視する自分の棋風がよく表れています。
さすがに囲いがゼロ枚になるので相手の反撃をしっかりと読む必要があります。
△7六歩▲6五桂△7五銀▲同銀△同飛の銀交換には▲1一歩成△同玉▲2四歩(第11図)があります。

①△同歩は▲2三銀
②△同角は▲2五銀
②△同角は▲2五銀
で後手陣は一気に危ない形になります。
実戦は△7六歩▲6五桂に△3三銀▲2六金△6五銀▲同銀右△3四桂▲2七金△1二玉(第12図)と桂の力で金を引かされましたが、▲3六歩と今度は桂頭に狙いを定めて攻めていきました。

以下、こちらの玉も薄いので怖いところもありましたが、勝ちきることができました。

投了図以下は△1二同玉▲1三銀成△同角▲同香成△同玉▲1四飛△同玉▲2五金△1三玉▲1四香までの詰みとなります。
本局のポイントは▲4七銀~▲5六銀と中央に厚みを築いたことで、その時点でやや作戦勝ちになっていると思います。
▲7八金は勇気のいる手ですが、左辺を受け止めてからの端攻めが見えているので、いい判断だったかと思っています。
"西山朋佳流"振り飛車の勝ち方を体系的に学ぶならこの本がおすすめ
ここまでお読みいただきありがとうございました!以上が"西山朋佳流"先手中飛車の勝ち方です。
詳しくは、2022年8月19日発売の『実戦で学ぶ振り飛車の勝ち方』(西山朋佳)に載っています。
本書ではほかにも、「三間飛車」や「相振り飛車」の勝ち方も解説しています。
ぜひ本書を読んで、"西山朋佳流"振り飛車の勝ち方をマスターしてください! 限定記事や限定動画など特典が盛り沢山!将棋情報局ゴールドメンバーご入会はこちらから
将棋情報局では、お得なキャンペーンや新着コンテンツの情報をお届けしています。