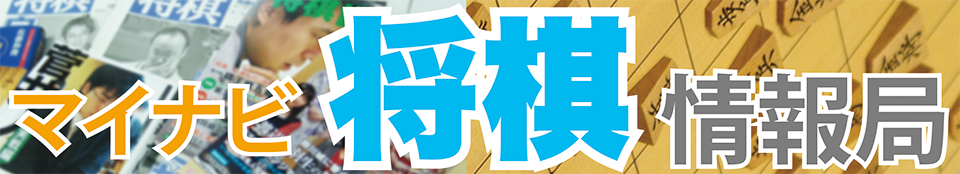河口俊彦先生との突然のお別れ。
私は出張帰りの新幹線の車中で、訃報を聞きました。背中の痛みを訴えて入院されたのは知っていましたが、その後、入ってきた情報では、わりと早くに退院できそうだとのことだったので、ひとまずほっとしていただけに、ショックはさらに大きくなりました。
倒れられた時、河口先生は、奥様を通じて真っ先に観戦記を掲載している新聞社と、「評伝・木村義雄」の連載を抱える将棋世界編集部に連絡させたそうです。特に、新聞観戦記は掲載中であっただけに深刻でしたが、先生は病院のベッドで最終譜を書き上げたそうです。告別式での奥様の挨拶は、このお話だけで締めくくられましたが、物書きとして最期まで責任を全うした河口先生の誇りを感じました。
柩の中の河口先生の安らかなお顔を見て、いろんなことを思い浮かべました。といっても私は先生の晩年しか関わっておりませんが、少し思い出を書かせていただきます。
河口先生の代名詞といえる「対局日誌」は、もともと『将棋マガジン』に長く連載されていた人気コーナーでしたが、『将棋世界』に引き継がれる形で「新・対局日誌」として平成7年1月号から連載が始まっています。当時の雑誌を見返してみると、「強力連載」と銘打たれ、いかに編集部が力を入れていたかが分かります。あとから知ったのですが、作家なみの待遇で迎えたようです。それほど欲しい連載だったのです。
コーナーの扉には、河口先生が自宅の書斎の机に座っている写真が掲載されています。棋士というよりも作家のような風体。私はこの写真が好きで、将棋連盟からお借りして現在発売中の最新4月号で使わせていただきました。撮影者が分からなかったのですが、「ヒゲのカメラマン」の弦巻勝さんから、氏が撮影した写真だというご連絡をいただきましたので、ここに記させていただきます。
さて、「将棋世界」に連載がスタートした当時、私は二十代半ばのフリーターで、日本将棋連盟の書籍課で校正のアルバイトをしていました。将棋会館3階事務局の窓際の隅っこのデスクで、毎日『羽生の頭脳』や『将棋年鑑』の校正をしていました。
私語ひとつなく黙々と仕事をしている我々のシマのおとなりの課が、将棋世界編集部でした。毎日、いろんな棋士やライター、カメラマンが顔を見せて活気がありました。
当時の編集長は大崎善生さん。のちに『聖の青春』や『将棋の子』で作家に転身されますが、この頃は連盟職員だったのです。いつも午後の3時頃にフラフラと出社され、編集部員とやりとりをしたり、仕事の電話など雑用をしたあと、6時くらいに棋士の方々の飲みの誘いにのって帰られます。デスクに座っているのはせいぜい3時間。編集長というのは、なんて楽な仕事なんだろうと思ったものです。いま考えれば、大崎さんが特別だっただけで、現編集長の私は毎日朝から晩まで働いておりますが。
当時はパソコンもウィンドウズもまだ普及しておらず、編集作業は昔ながらのアナログ方式でした。原稿はもちろん用紙に手書き。DTPなんて便利なものはもちろんなく、届いた原稿を、編集部員が赤ペンで整理したあと、割り付け(レイアウト)して、印刷所に入稿するという流れでした。
河口先生の取材は、月に3~4回。夕方頃に編集部にやってきて、編集部員と雑談をしたあと、上の対局室に上がって観戦されます。先生はよくしゃべるので、雑談がこちらの耳にも入ってきます。ゲラに目を通しながらそのお話を聞くのが楽しみでした。
よく覚えているのは、「いま、渡辺明っていう子が奨励会で勝ちまくっているんだけど知っているかい? まだ11歳なんだけど、入会から半年で2級に昇級したんだ。羽生なみの才能だよ」と嬉しそうに話されていたこと。対局日誌を通じて、谷川浩司、羽生善治ら大きな才能の誕生を書いてこられた方だけに、新しい金の卵を発見した喜びが感じられました。
私はその後、縁あって将棋世界編集部の一員になりました。ある時、河口先生はペーペー編集部員の私に向かって、「なあ君、錐の嚢中に処るが如し(きりののうちゅうにおるがごとし)っていう言葉を知っているかい?」と話しかけてきました。当然ながら無知な私がポカンとしていると、「ダメだなあ~。そんなことじゃ一人前の編集者になれないよ」と呆れた顔で苦笑していました。
中国の古い言葉で、「尖った錐の先は、袋に入れても外に突き出てしまうように、本当の才能は隠れていてもいつか必ず真価を現す」という意味だということをあとで知りました。どういったシチュエーションでそんなことをお聞きになったのかは忘れましたが、渡辺明さんを例えていたのではないかと思います。
河口先生の原稿は、いつも締切ぎりぎりになってFAXで届いてきました。先生は、ペラ(200字詰め原稿用紙)で数枚ずつ書いては書いては送り、それを待ち受けていた担当編集者が順次、割付用紙にレイアウトしていきます。時折、いまどのくらい行数を書いたか、残りは何行かを電話でやりとりしながら、10ページぴったりにまとめるところが名人芸でした。字は達筆で読みにくいですが、ゲラになって出てくると、とても面白い内容で、さすがだなあと感心していました。
個人的な楽しい思い出は、いまから15年ほど前になりますが、泊りがけの京都旅行に誘ってくださったことでしょうか。ペーペー編集者の懐を気遣い、現地での移動費と飲食代は先生が持ってくださいました。
阪田三吉贈名人・贈王将が、木村義雄先生や花田長太郎先生と勝負将棋を戦った有名な南禅寺や天龍寺をはじめいろんな場所を散策しました。若い頃に、登山や社交ダンス、ゴルフなどにいそしんでいた河口先生は、とにかくよく歩きます。夜は、新進女優の実家で有名な料亭で食事。河口先生は下戸ですが、京都の楽しみ方を面白おかしく聞かせてくださいました。自分にとっては学ぶことの多い忘れらない旅でした。
大崎さんが職場を去り、編集長が2年置きに変わるようになると、部数回復のためさまざまな誌面刷新が試みられ、その一環として「新・対局日誌」もそろそろ……という話になりました。編集長が変わるたびに、「どうするの? 俺はまだ書いていいのかね?」と冗談めかして仰っていましたが、いざ終了を告げられると、いつもと変わらぬ笑顔の中にも寂しさが窺えました。
その後は、しばらく編集部とは距離をおかれるようになり、時おり単発の観戦記をお願いすることはあったものの、お話をする機会も減りましたが、私が編集長に就任したときには喜んでくださいました。
時は巡り、一昨年の春のある日、将棋会館で先生とばったりお会いした時に、「木村義雄十四世名人のことについて書いてみたいんだけど」と相談を受けました。木村名人については、若い頃に出版した自伝以外に評伝といった類の本がないなあと思っていたので、二つ返事でお願いすることにしました。それが、亡くなるまで連載した「評伝・木村義雄」です。
「連載は長くなると思うけど、いいかい?」と仰っていましたが、今年3月号掲載の第20回「高野山の決戦」が最期の原稿となってしまいました。木村名人の棋士人生を辿りながら、将棋界の黎明期、戦後の復興、隆盛への道を描き、これからどういう展開になるのか楽しみにしていたのですが、読者のひとりとして残念でなりません。私は、河口先生はこの連載を通して、別の何かを書き残しておきたかったのではないかと考えています。それが何だったのか、今となっては知るすべはありません。
連載がスタート頃、突然、木村名人のご息女から「父のことを書いてくださってありがとう」との連絡が届きました。ご高齢ながら、まだ木村名人のご実家でお元気に暮らしておられることを知って大変驚いた私は、河口先生に取材を兼ねて訪ねてみたいですねと伝えました。先生は「暖かくなってからだなあ」と仰っていたのですが、それも叶わなくなりました。
先生は、いつまでもお元気な方だと思っていました。3年前、横浜で行われた王座戦で、買ったばかりのiPadを自慢気に見せ、「これ、面白いね。いろんな将棋が見られて楽しくてしょうがないよ」と笑っていましたが、衰えを見せない好奇心に感心し、自分もこうありたいと思いました。
体調を崩される半月前、先生から「お歳暮ありがとう。田名後君が結婚したことを最近知ってびっくりしたよ。おめでとう」とのお便りをいただきました。このハガキは生涯大切にいたします。
河口俊彦先生、どうもありがとうございました。
将棋世界編集長 田名後健吾
マイナビ出版の雑誌・書籍の紹介サイト