2022.07.21
細かすぎて伝わらない!『令和4年版将棋年鑑』藤井聡太インタビューの微妙なニュアンスの補足 第3回
(1)身近に竜王
(2)詩人・藤井聡太
(3)まだまだ足りない
将棋年鑑に掲載された藤井聡太竜王のインタビューの非言語的な部分を言語化して伝えようとする野心的な試み、細かすぎて伝わらないシリーズ。第3回の時間がやってまいりました。
まず、今この記事を読んでいる方を、気持ち悪さのふるいを潜り抜けてきた猛者と認定させていただきます(笑)。そんな藤井指数の高い皆さんの期待に応えるべく、今回も全力で行きます。
先に断って(謝って)おきますが今回長いです(;^_^A
どうぞ最後までお付き合いのほど、よろしくお願いします。
第3回のMENUは以下の通りです。
(2)詩人・藤井聡太
(3)まだまだ足りない
今回もテレビ、冷蔵庫、洗濯機と3種取り揃えております。
それでは早速まいりましょう!
(1)身近に竜王
第3回の切り込み隊長は「身近に竜王」です。これは皆さんからご応募いただいたシンプルな質問シリーズの一つ、「トランプで1番好きな遊びは?」という質問で現れたやり取りです。
――では続いて、トランプで1番好きな遊びは?
「大富豪です」
――メジャーどころですね。理由はありますか?
「大富豪が一番運と戦略のバランスがいいかなと思います。7並べとかだとカードによっては、かなり手段が限られてしまうので。大富豪ならカードが弱かったら弱いなりの戦い方が、なくはないという(笑)」
最後の「なくはないという(笑)」の(笑)は「とはいっても運の部分が大きいですけどね」の意味の笑いですね。
面白かったのはここからです。
――大富豪にはいろいろなローカルルールがありますが、どんなルールでやっていましたか?
「うーん。何が普通のルールなんでしょう」
――8とか、11とか……。
「8切り、イレブンバックは多いですよね」
藤井先生の口から私が小学生のころから慣れ親しんだ単語が聞けたことで、「藤井先生も大富豪で育って来たんや」と謎の親近感を覚えてしまいました。
なんとなく話が盛り上がり、さらにルール確認は続きます。
――あとは縛りをつけるかどうか。数字縛り、マーク縛り。
「縛り、アリ派でしたね」
――ジョーカーにスペードの3が勝てる、というのもありますね。
「あ、スペ3もありました」
トランプは小学生の頃にお友達とやったのか、お正月などに親戚の皆さんとやったのかわかりませんが、藤井先生はきっと大富豪も全力でやったことでしょうし、負けるのは嫌いだったのではないかと推察します。
「よし、ここでスペサンを出して革命して、ヤギリで勝ちだ!」と詰み手順を発見して喜ぶ藤井少年を妄想して、一人ほくそ笑んでいる自分がいました。

(2)詩人・藤井聡太
幸先よく気持ち悪さのスマッシュヒットが決まったところで、2つ目のテーマにまいりましょう。続いては「詩人・藤井聡太」です。これは會場担当の詰将棋パートで現れた部分になります。
今回は詰将棋と言いながら昨年から藤井先生が始められたという「チェスプロブレム」についても語っていただきました。まず、「なぜチェスプロブレムを始めたのか」というところから話を切り出します。
――去年の12月に、チェスプロブレムに取り組まれているというお話をされていました。チェスプロブレムを解くようになったきっかけはありましたか?
「明確にあるわけではないんですけど、最近は詰将棋でもチェスプロブレムからテーマを輸入していたり詰将棋とチェスプロブレムの関連が強くなっているので、それではチェスプロブレムとは何ぞやということを知らないといけないのかなと」
話の本筋と全然関係ないんですが、「きっかけはありましたか?」という質問に対して「明確にあるわけではないんですけど」から話し始めるのが、いかにも藤井調でたまらないです。
チェスプロブレムを始めたきっかけは詰将棋にあったんですね。詰将棋をより深く知るためにチェスプロブレムも学ばねばならぬと。日本史をより詳しく知るために世界史も学ぶ、みたいな感じでしょうか。知的好奇心にあふれていて素晴らしいですね。
そしてこれも本筋と関係ないんですけど「チェスプロブレムとは何ぞや」という文語的な表現を会話で使う藤井先生がたまらないです。時々こうやって小説に書いてあるような言い回しを使われるので編集者島田としては、そのたびにキュンキュンします。
すいません、もだえてばかりで話が進みません。
私が伝えたかったのはこの後の話。「詰将棋とチェスプロブレムの違い」についての藤井先生の回答です。
――チェスプロブレムと詰将棋でここは違うというところがあれば教えてください。
「得意な表現が違うという印象は受けました。チェスプロブレムは変化を含めて何かのテーマを明確にすることが多いですけども、詰将棋だとフォーマットそのものではない、手の流れだったりそういうところに魅力がある作品も多いので、それぞれの得意な表現を生かして、今後も詰将棋でもチェスプロブレムでも面白いものが出てくるのかなと思って楽しみにしています」
・・・言っていることがとても難しいです。これは、このシリーズ始まって以来、真っ当な意味での「インタビューの補足」が必要な場面がやってきたかもしれません(笑)
まず、チェスプロブレムはテーマ(問題の意図)が決まっていて、そのテーマを手順で表すものであると。シンプルで合理的な印象でしょうか。
詰将棋にももちろん「テーマとその表現」というフォーマットはあるんですが、詰将棋の場合はそれを表現する際に「手の流れ」という別の魅力も出てくると。
では「手の流れ」とは何か?ということですが、例えば合駒で発生した桂馬が2回連続で跳ねるような、指し手の連続性みたいなものです。藤井先生は2年前の将棋年鑑のインタビューでも自分の好きな詰将棋について「何というかその捨て駒でも単発ではなくて、やはりストーリー、流れがあるというのが大事」とおっしゃっていました。
指し手が点ではなく線として意味を持って有機的につながっているのがお好きなんですね。
チェスプロブレムが目的志向が強いのに比べて、詰将棋には過程の手順から醸し出される抒情的な魅力があるということが言いたいのだと思います。
チェスプロブレムと詰将棋がかなり似た性質のものであるため、その違いとなると相当細かい話になるのですが、そこをあえて突っ込んでいった會場と、美しい回答を披露してくださった藤井先生に拍手を送りたいです。
ちなみに、偉そうに語ってますがインタビュー中私は藤井先生が何を言っているのかさっぱりわかりませんでした(笑)
あとで會場に「あれ、藤井先生何が言いたかったの?」と聞いて、説明されてようやくわかった次第です。ありがとう、會場先生。
今後はインタビュー中、もだえすぎないように気を付けます。

(3)まだまだ足りない
さて、フィナーレを飾るのは「まだまだ足りない」です。書いているうちに(1)、(2)が想定より遥かに長くなってしまい、今回は(2)までで終わりにしようかなとも思いましたが、「気持ち悪さが足りない」という謎のエールが聞こえてきましたので、最後に最大級に気持ち悪い花火をドカンと打ち上げたいと思います。
これは竜王戦第4局のお話で出てきたものです。前回「一生懸命考えることができた」という涙なしには聞けないセリフを紹介しましたが、そのあとのやり取りになります。
竜王戦第4局を取り上げたNHKスペシャルについてズバリ聞いてみました。
――NHKスペシャルの局後のインタビューで対局者のお二人から「もう少し続けたかった」という同じ感想が出たのは驚きでした。
「そうだったんですか」
――棋士が局後に「もう少し続けたかった」ということ自体が珍しいと思うんです。
「はい」
――それを二人がそろって言うというのはさらに珍しいと思って。
「なるほど、はい」
話は続きます。
――対局中に豊島先生と思考がシンクロするような感覚があったんですか?
「いや、そういう感覚はなかったですけど、自分は対局中にあの局面の重要な変化の半分かそれ以下しか読めていなかったと思います。そういう意味では本当はこの先どうなっていたんだろうという気持ちはありました」
さて、ここからが本題です。私は昨年の将棋年鑑のインタビューで、藤井先生の尽きることのない向上心の源泉について「強くなるからこそ見える世界があるかもしれない」というお話を聞きました。そして、この竜王戦第4局こそ、「強くなったからこそ見えた世界」なのではないかと考えていました。
なぜなら、あの超難解な局面は藤井先生と豊島先生が非常に高いレベルで拮抗していたからこそ現れた局面だったからです。
今回のインタビューで私が一番聞いてみたかった質問。それを、藤井先生にぶつけてみました。
――以前のインタビューで将棋を続ける理由として「強くなるからこそ見える世界があるかもしれない」とおっしゃっていました。この竜王戦第4局はまさにお二人だから到達できた境地のように思いましたが、藤井先生はどう感じましたか?
頭のいい藤井先生ですから、私の持って行きたい話の方向性はすぐにわかったと思います。私としては「確かにあの1局はそういう世界の片鱗がみえた対局だったかもしれません」というような答えを期待していました。
しかし、藤井先生少し間を取った後にこう答えました。
「あの一局に関しては途中有利になったのを生かせなかったというのがあるので、ずっと難しくて最後にああいう局面が現れたら理想的なのかなと思います」
・・・やっぱり藤井先生は藤井先生でした。名局賞に選ばれ、多くの棋士が絶賛したあの将棋にも満足していなかった。
というか、あの竜王戦第4局でさえ藤井先生にとっては「課題が見つかった対局」の1つに過ぎないのでしょう。
答える前に間があったのは私の期待がわかったからだと思います。
「島田さんの求めてる答えはわかります。でもすいません。自分の気持ちにウソはつけません」
と考えておられたのかなと。藤井先生の優しさと正直さを深く感じて、涙をこらえることができませんでした。
インタビューには続きがあります。
――まだまだ足りない、という感じでしょうか。
「そうですね」
これが藤井聡太です。
もう、一生推しです。
竜王をストレートで奪取しても、名局賞を取っても、NHKで特番を組まれても「まだまだ足りない」。
もっと先へ、もっと上へ。
やっぱり、自分の尺度で藤井先生を測っちゃいかんのだなと。
藤井先生は藤井先生のままで、どこまでも高く羽ばたいてほしい。
そう思ったあの夏の日でした。
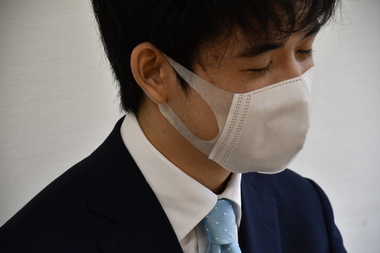
=====================================
以上で第3回は終了となります。
もうだいぶお腹いっぱいになったと思いますが、いかがでしょう?
まだまだ足りないでしょうか(笑)
あと1回、将棋年鑑が発売するまでになんとか書ければなぁと思っております。
それまで皆さんどうかお元気で。またお会いしましょう。
(霧の中の第4回に続く)
限定記事や限定動画など特典が盛り沢山!将棋情報局ゴールドメンバーご入会はこちらから


