2017.05.16
驚愕必至!増田康宏四段インタビュー
増田康宏四段による「堅陣で圧勝!対振り銀冠穴熊」の発売を記念し、特別インタビューをさせていただきました。増田四段から発せられる驚きの言葉の数々、とくとご覧あれ!

――よろしくお願いします。
「よろしくお願いします」
――まず、今回の本のテーマである銀冠穴熊戦法について、教えてください。「はい。対振り飛車の戦法で、銀冠に囲ってから穴熊にするのが大きな特徴です」
――普通銀冠穴熊といったらまず穴熊にして、それを発展させてできるものですよね。「そうです。通常の銀冠穴熊とは違い、まず銀冠にして囲いを安定させてから、機を見て穴熊に潜る、というのが特徴です。また、普通穴熊は角道を自ら止めてから囲うものですが、この戦法では角道を開けたまま駒組みする、というのもこれまでにないところかと思います」
――角道を開けたまま駒組みすることにはどのようなメリットがあるのでしょうか?「▲6六歩と角道を止めてしまうとどうしても囲いが弱体化してしまいます。歩はできるだけ下にあった方が堅いですから」
――なるほど。とはいえ、角道を開けたまま戦うということは常に角交換される心配もあります。その辺りは大丈夫なんでしょうか?「そこは書籍を読んでいただければ(笑)。確かにそれが一番嫌なんですが、角交換は大丈夫です」
――相手が角交換してきても戦えるし、角交換してこなければ、自分だけどんどん堅くできると。いいことしかありませんね。「そうですね」
(以下、真面目なインタビューの続きは将棋世界7月号に掲載されます)
堅陣で圧勝!対振り銀冠穴熊
増田康宏
紙の本:1,663円
発売日:2017年6月19日
――さて、ここからはざっくばらんに質問に答えていただき、謎のベールに包まれた増田四段の正体を解き明かしていきたいと思います。

Q1、将棋のルールはいつ覚えましたか?
「5歳です。母に教わりました」
――珍しいですね。お母様がルールを知っていたんですか?「いえ、母も知っていたわけではなく、一緒にルールを覚えました」
――小学校に上がる前に将棋を覚えて、お母さんに勝つようになって、その後は?「すぐに地元の大会に参加して、小学校2年くらいには道場に通っていたと思います」
――早いですね。でもさすがに道場では負かされたんですよね?「いや、それが勝てたんです」
――ホントですか。すごいですね。初段になったのはいつ頃だったんですか?「道場にいった初日に初段に認定されました」
――はぁ~。小2で初段ですか。では小3で四段、みたいな感じですか?「いえ、小2で四段になっていました」
――むちゃくちゃですね。小学生時代は何か大会で優勝されたとかありましたか?「3年生のとき倉敷王将戦の低学年の部で優勝して、4年生のとき高学年の部で優勝しました」
――成長が早すぎて、怖いです。Q2、最初にしてしまった反則は?
「反則、したことないんですよ」
――えーー!?そんな人がこの世にいるんですか!「ええ、ないと思います」
Q3、プロになろうと思ったのはいつですか?
「小学校3年生くらいです」
――増田先生のお師匠といえば森下卓九段ですが、森下先生とは以前からお付き合いがあったのですか?「いえ、奨励会を受験することになって、道場の席主の方が森下九段がいいのではないかと推薦してくださいました」
Q4、最初に知ったプロ棋士は?
「羽生先生と、森内先生です。通っていた道場の関係で知りました」
Q5、得意戦法は?
「(少考して)銀冠穴熊です」
――そうなりますよね(笑)。他にはいかがでしょうか?「最近だと、雁木です」
――が、雁木!?雁木ですか。「はい。矢倉は終わりました」
――ホントですか?矢倉って終わったんですか?矢倉の何がダメなんでしょうか?「桂馬が使えないんですよ、矢倉は。▲6六歩・7七銀という形にすると7七の銀は基本的に動けなくなります。これでは桂を飛ぶスペースがありません」
――玉側の桂のことですよね。▲7七桂と跳ねたいということですか。「跳ねるかどうかは分かりませんが、跳ねる余地があるということが大きいんです。あと、雁木は囲いのバランスがいいですね。矢倉は偏ってしまうのでダメです」
――はぁ~。そういうものですか。Q6、普段は指さないものの、興味のある戦法は?
「ないです」
――ないんですか(笑)。先生は振り飛車はまったく指されないんですか?「奨励会に入る前は少し指してたんですが、師匠から居飛車を指すように言われまして、それからは居飛車しか指してません。2手目△8四歩なので、矢倉か角換わりだけですね」
――ストイックですね。Q7、憧れの棋士は?
「升田幸三先生です」
――名前が同じ「ますだ」ですね。「それもあるんですが、あの時代で将棋に対して非常に進んだ考え方を持っていたと思うので」
――特に印象深い対局や一手はありますか?「△4四銀です」
※第17期名人戦第7局で升田名人が指した△4四銀(下図)のこと

――この手で先手の狙いをすべて封じたという一手ですね。
「そう、それです。三冠王時代の升田先生は別格の強さだと思います」
Q8、好きな将棋の格言は?
「特にないです」
――ないんですか(笑)?「ええ、格言とか、あまり学んでこなかったのでよく知らないんです」
――「玉の早逃げ八手の得」とかあるじゃないですか。格言を軸に考えたことがない、ということでしょうか。「そうです。格言、意味ないですよ。場合によるじゃないですか。最近は玉と飛車が接近したほうがいいこともありますし。柔軟な考え方ができなくなります」
――なるほど。Q9、将棋のどの部分を伸ばしたいですか?
「(少し考えて)粘りですかね」
――粘り・・・ですか。序盤とか終盤という答えを想像していたので少し驚きました。悪くなってからの粘り、ということですよね?「そうです。最善を続けて離されずについていくということですね」
――この人の粘りを参考にしたいな、という棋士はいますか?「いえ。すごいと思うのはコンピュータの粘りです。コンピュータだから当然なんですが、悪くなっても心が折れずにその局面での最善手をひたすら続けていくので」
――なるほど。そういうことですか。Q10、好きな駒は?
「金です」
――理由はありますか?「守りの中心なので」
Q11、影響を受けた将棋の本は?
「真部先生の『升田将棋の世界』です。将棋の解説もいいですし、読み物としても楽しめました」
Q12、練習将棋やネット対局を含めて1週間に何局くらい指していますか?
「5局くらいですかね」
――想像していたより少ないです。もっとバンバン指しているのかと思っていました。「あまり局数を重ねても仕方ないと思っているので。長い持ち時間でしっかりやったほうがいいと思っています」
――ではネット将棋も指されない?「そうですね。以前は将棋倶楽部24で指していたのですが、最近はまったく」
――研究会もされない?「そうですね。行くのが面倒ですし」
――ん?と、なると誰と指しているんですか?「コンピュータと指しています。今は『激指』とやっています」
――『激指』!!うちのソフトじゃないですか!ありがとうございます。「『激指13』です」
――じゅ、じゅうさん!?最新版の14ではなく?『激指14』差し上げますよ。「いや、やはり13を攻略してからでないと」
――増田先生でも13が攻略できてないんですか。「局面によっては、なかなか勝てません」
――激指って強いんですね・・・。今更ですけど。Q13、詰将棋はどれくらい解きますか?
「解かないです」
――解かない!? 解かないって、どういうことですか!ホントに、全く解かない?「本当です。全く解きません」
――あまりの衝撃に倒れそうです。「これ、言うと変な目で見られるんですけど、詰将棋、意味ないです」
――!!将棋界に激震が走りましたよ、今。なぜ詰将棋を解かないんですか?「実戦に出てきませんから、詰将棋は。それなら実戦に出てきた詰み筋を学んだほうがためになります」
――確かにそういう考え方もありますか。しかし解いてないというのには驚きました。ちなみに、昔から解かないんですか?「いや、小さい頃はめちゃくちゃ解いてました。でも三段のときくらいにやめて、それからは解いてないです」
――なるほど。それを聞いて少しだけ安心しました。Q14、これまでで勝って一番嬉しかった将棋は?
「やはり新人王戦の決勝ですね」
Q15、これまでで負けて一番悔しかった将棋は?
「AbemaTVの藤井四段戦です」
――注目された対局でしたからね。「生まれて初めて年下に平手で負けました」
――なんと!そうなんですか。増田先生が19歳、藤井四段が14歳ですか。増田先生から見て藤井四段はどうですか?「序盤がうまいです。普通若いと序盤は粗いとしたものなのに、しっかりしてます」
――先生と対戦した将棋、観戦してましたけど終盤の▲9七玉にはびっくりしました。「あれは・・・不覚でしたね。あんなに強くなっているとは思いませんでした」
――あ、以前にも対局したことがあったんですか?「はい。藤井四段が三段になったときに一度。そのときは勝ちました。今回もまぁ勝てるだろうと思ってたんですが、自分の想像以上に強くなっていました」
――炎の七番勝負は終わってみれば6勝1敗で羽生先生にも勝ったわけですからすごいですよね。「ただ、今回は対局相手の皆さんが様子を見ていた、というか引いていた部分はあったと思います。羽生先生も仕掛けられて一方的に悪くなってしまい、公式戦では見られないような負け方をされていました。そういう意味でも勝負はこれからです」
Q16、将棋のどんなところが好きですか?
「いろいろな選択肢があるところです」
Q17、棋士としての今年度の目標は?
「今勝ち進んでいる竜王戦での活躍と順位戦の昇級が目標です」
※インタビュー時、5組決勝戦前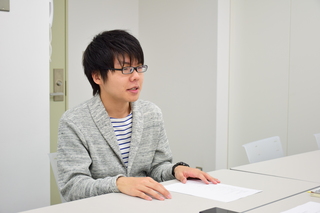
ここからはあまり将棋に関係ない質問です。
Q18、得意な課目は?
「あまりないですが、強いて言えば社会でしょうか」
Q19、苦手な課目は?
「美術です」
Q20、好きな女性のタイプは?
「優しい方」
Q21、自分の性格を一言で言うと?
「穏やかかなと思います」
Q22、ストレス解消法は?
「そもそもストレスがたまらないです」
Q23、好きな映画は?
「マネーボールです」
Q24、子どもの頃のあだ名は?
「まっすーです」
Q25、今一番欲しいものは?
「高性能のコンピュータ」
Q26、よく聞く音楽は?
「YUIさん」
――どういうところが好きですか?「結構暗めの曲が多いんですよね。三段時代に聞いて、いいなと」
Q27、趣味は?
「ピアノです」
――ピアノですか!「習ってたんですよ。小学生の頃から」
――今でも弾くんですか?「たまに弾きますけど、だいぶ腕は落ちました。熱心にやっていたときはコンクールで入賞したりもしていたんですが」
――はぁ~すごい。では、一時期は将棋を取るかピアノを取るかで悩んだり?「いや、そこまでではないです(笑)」
――どんな曲を弾くんですか?「今はそれこそYUIさんとか、J-POPです」
Q28、将棋をやっていなかったらどんな職業についたと思いますか?
「この質問よくされるんですけど難しいですよね。子どもの頃から将棋だったので」
――これからもよくされる質問だと思うので、ここで考えましょう。「将棋がなかったら・・・。囲碁棋士ですかね」
――いや、近い近い(笑)。でも面白いからそれでいきましょう。――今日は長々とありがとうございました。書籍のことも先生ご自身のことも語っていただきありがとうございました。とても面白かったです。
「こちらこそどうもありがとうございました」
限定記事や限定動画など特典が盛り沢山!将棋情報局ゴールドメンバーご入会はこちらから

