2022.09.12
私はiPhoneやiPadを中心としたテクノロジーに関する情報支援を行うオンラインラウンジを、視覚障害者に向けて毎月開催しています。ラウンジでは毎回、前半はテクノロジーを生み出してきた方にインタビューしながら支援機器の開発秘話などを紹介してもらい、後半は視覚障害者の講師によるテクノロジー活用に関するQ&Aの時間を設けています。新型コロナウイルスの流行前は数名程度であった参加者が、現在では毎月100名以上の視覚障害者や支援者、技術開発者が参加しており、大盛況となっています。
現在ではSiriやスマートスピーカなどの普及もあり、音声を介した端末操作は一般化しつつあります。我々が音声で便利に端末を操作できるようになった背景には、ある一人の視覚障害者の願いから始まる壮大な開発物語が存在します。今回は音声読み上げソフトウェアを開発した視覚障害者、株式会社アクセステクノロジーの代表取締役・斎藤正夫さんについて紹介します。
アクセステクノロジーは、ソフトウェアの研究・開発・製作・販売、コンピュータ関連機器の設計・製作・販売を通して、視覚障害者の情報環境・社会参加への道を開拓している企業。斎藤さんは、真空管、トランジスタ、集積回路を自らいじるほどの機械好きであり、「なんでも自分で作りたい」と考える性格でした。
アマチュア無線が趣味だった斎藤さんは、通信で世界中の人々とつながれることに喜びを感じる一方で、通信後に取り交わすQSLカード(交信証)の記載が、視力低下のために読みづらくなっていました。そのような中、1980年代初期にパソコンが普及したことで「これを使えば解決できるのでは」と考えたそうです。
しかし、パソコンを使おうにも、画面読み上げ機能などまだ存在しない時代。プログラムを自分で考えては、まったくフィードバックのないパソコンに打ち込む毎日を過ごしていました。うまく動いたら思ったとおりの音が出る一方、1カ所でも間違っていたら反応しないという試行錯誤を繰り返す日々。そのような中で、言語として識別しやすいモールス符号を用いて、画面上の文字を音で出力するプログラムを作り上げました。
当初はBASIC言語を用いて開発していましたが、それではほかのプログラムを音で出力してくれません。そこで、マシン語による開発に移行。このときも試行錯誤の連続で、命令を入力し、結果を見て動作を推測しました。そしてパソコン購入から5カ月目の1983年12月、キーを打ったら即座に音が出るプログラムが完成。その後斎藤さんは知人からの依頼に応じて、さまざまなパソコン機種と音声合成器へ対応したプログラムを次々と開発しました。このときプログラムに付けたファイル名が「VDM」。VDは画面を音声出力する「ボイス・ディスプレイ(Voice Display)」の略で、Mはマシン語に由来するそうです。
そうして画期的なMS│DOS用のスクリーンリーダ「VDM100」は1987年12月に完成。視覚障害者である斎藤さん自らが開発し、改良の依頼に即座に対応するVDM100はユーザの支持を得て、広く普及しました。
斎藤さんとの対談を通して、建具職人の父親のもとに生まれ、「自分で使う物は、自分で作る」ことが普通であったという家庭環境が、その不屈の精神と創造性に溢れた超人を作り上げたのだと感じました。アマチュア無線からインターネットへと形を変えて、人がつながる楽しさを届ける斎藤さん。モノが簡単に買える時代だからこそ、作ることの大切さを見つめ直すべき時代が来ているのかもしれません。
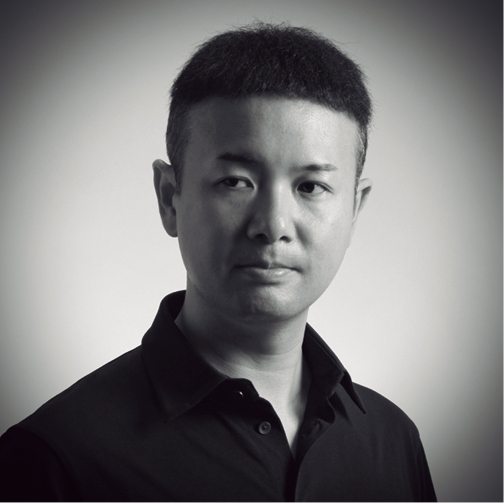
Taku Miyake
医師・医学博士、眼科専門医、労働衛生コンサルタント、メンタルヘルス法務主任者。株式会社Studio Gift Hands 代表取締役。医師免許を持って活動するマルチフィールドコンサルタント。主な活動領域は、(1)iOS端末を用いた障害者への就労・就学支援、(2)企業の産業保健・ヘルスケア法務顧問、(3)遊べる病院「Vision Park」(2018年グッドデザイン賞受賞)のコンセプトディレクター、運営責任者などを中心に、医療・福祉・教育・ビジネス・エンタメ領域を越境的に活動している。また東京大学において、健診データ活用、行動変容、支援機器活用関連の研究室に所属する客員研究員としても活動中。主な著書として、管理職向けメンタル・モチベーションマネジメント本である『マネジメントはがんばらないほどうまくいく』(クロスメディア・パブリッシング)や歌集・童話『向日葵と僕』(パブリック・ブレイン)などがある。



