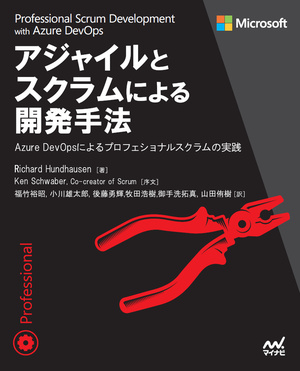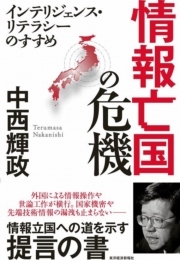アジャイルとスクラムによる開発手法
Azure DevOpsによるプロフェショナルスクラムの実践
マイナビ出版
よりプロフェッショナルなスクラム開発の実践へ
よりプロフェッショナルなスクラム開発の実践へ本書は、著者が長年スクラムチームをリードしてきた実践経験をまとめあげ、スクラムを習得するためのヒントやコツを多数紹介したProfessional Scrum Developmentの翻訳書です。Azure DevOpsを使用しさらなる改善を目指しているのであれば本書は最適です。アジャイル開発において最も使用されているフレームワークが「スクラム」です。本書は、著者が長年スクラムチームをリードしてきた実践経験をまとめあげ、スクラムを習得するためのヒントやコツを多数紹介した「Professional Scrum Development with Azure DevOps」の翻訳書です。抽象的な内容を具体的な方法へ落とし込み、開発者が高い価値のプロダクトを提供する方法、複雑な問題を解決する本質的な方法を解説します。
スクラムを実践する際には、手間を最小限に抑え機動的で滑らかにチームが働くことを可能とする使い勝手の良いツールの選定とその使用方法が非常に重要となります。そのツールの1つが本書で解説するMicrosoft Azure DevOpsです。スクラム開発の概要を把握し"スクラムガイド"を読んだ上で、スクラム開発の具体的な実践方法の一例を学ぶべく本書を活用することをおすすめします。
[第1部] スクラムの基礎
第1章 プロフェッショナルスクラムとは
第2章 Azure DevOpsとは
第3章 Azure Boardsとは
[第2部] プロフェッショナルスクラムの実践
第4章 プリゲーム
第5章 プロダクトバックログ
第6章 スプリント
第7章 テスト駆動型計画
第8章 コラボレーション
[第3部 ]改善手法
第9章 フローの改善
第10章 継続的改善
第11章 大規模なプロフェッショナルスクラム
発売日:2022-06-28
ページ数:448ページ
目次
[第1部] スクラムの基礎
第1章 プロフェッショナルスクラムとは
第2章 Azure DevOpsとは
第3章 Azure Boardsとは
[第2部] プロフェッショナルスクラムの実践
第4章 プリゲーム
第5章 プロダクトバックログ
第6章 スプリント
第7章 テスト駆動型計画
第8章 コラボレーション
[第3部 ]改善手法
第9章 フローの改善
第10章 継続的改善
第11章 大規模なプロフェッショナルスクラム
著者プロフィール
-
Richard Hundhausen(リチャード・フンドハウゼン)
Accentient社の代表を務め、ソフトウェア企業やチームに対してAzure DevOpsとスクラムの教育を提供している。プロフェッショナル・スクラムのトレーナーであり、「Nexus Scaled Scrum」フレームワークの共同開発者でもある。ソフトウェア開発者、コンサルタント、トレーナーとしての約40年にわたる経験に基づき「ソフトウェアはプロセスやツールではなく、人々によって作られ提供される」という考え方を大切にしている。
絶賛!発売中!
-
- 日産 驚異の会議
-
- 漆原次郎(著者)
- ビジネス・経済 読み物
- 自動車産業の苦戦から一気に抜け出してきた日産。エコカー競争でも電気自動車リーフに話題が集中している。この勢いの秘密は驚くべき会議手法にあった。会議好きも会議嫌いも感動する“すごい”会議!
-
- 凋落 木村剛と大島健伸
-
- 高橋篤史(著者)
- 日本社会・日本政治
- SFCG(旧商工ファンド)の大島健伸と日本振興銀行の木村剛。彼らはどのように一時の成功者となり、転落していったのか。2人の人生をたどりながら、他人を犠牲にした個人主義の蔓延に警鐘を鳴らす。
-
- 情報亡国の危機
-
- 中西輝政(著者)
- ビジネス・経済その他
- 「外交とは情報戦争である」「情報なき国家は、頭脳なき国家」との認識が世界の常識となっている。情報史の権威が、日本の危機と今後の国家情報戦略のあり方を提示する。
7212件中 7057-7060件目先頭前へ1761176217631764176517661767176817691770次へ最後
Copyright © Mynavi Publishing Corporation