
「ぼくらの福岡移住計画 2014 in TOKYO」レポート
東日本大震災以降、クリエイターにとって「どこで、どのように働くか」が「何をつくるか」に並ぶほどの意味を持つようになってきた。福岡市が主催、Smart Design AssociationとWeb Designingが事務局となり、3月29日(土)に「ぼくらの福岡移住計画 2014 in TOKYO」が開催された。このイベントは、近年注目を集める「東京から福岡への移住」に対して、官と民が一体でサポートする場として企画され、盛況を博した。当日の模様をレポートしよう。
Photo:五味茂雄(STRO!ROBO)




ぼくらの福岡移住計画 2014 in TOKYO
主催:福岡市 事務局:Smart Design Association、Web Designing
このイベントは、東京を中心に働くデジタルクリエイターやエンジニアを対象として、福岡で働くことを現実的に考えるために企画されたもの。実際に福岡へU/Iターンをしたクリエイターの声を通して福岡への移住転職を来場者とともに考える「住の部」と、福岡に会社を構える8社による出展/プレゼンテーションや転職エージェントも参加して来場者との交流を図る「職の部」の2部で構成されている。
また、2015年に入居人員およそ1,000人規模となる福岡社屋の建築計画を発表し、九州を中心とした新規人材確保を進めるLINE(株)より、LINE Fukuoka(株)の取締役でもある池邉智洋氏と、米インテル社が主催する次世代UIコンテスト「インテル Perceptual Computing Challenge」でグランプリを獲得した(株)しくみデザインの中村俊介氏が登壇し、キーセッションを行った。
来場者と出展企業がフランクに対話を図った交流会では、髙島宗一郎福岡市長と(株)ケンコーコム後藤玄利社長によるスペシャルトークが用意されるなど、非常に豪華な催しで来場者に福岡への移住を具体的に考えるきっかけを提供した。
第1部 住の部 プレゼンテーション&トークセッション
登壇者:カズワタベ氏(プランナー/ディレクター)、畠山千春氏(新米猟師/ライター)、下村晋一氏(Webエンジニア)、毛利慶吾氏(編集者/プランナー)
ファシリテーター:村上純志氏(NPO法人AIP)、馬場静樹(Web Designing編集長)

第1部では、福岡へ移住したクリエイター4名による個別プレゼンテーションとトークセッションが行われた。
トークセッションは「福岡の魅力」と「福岡に移住することのメリットとデメリット」を軸にして進行。中心地は歩いて回れる範囲にさまざまなスポットが集中しているうえ、空港からも近いという立地のメリットや、すぐ近くに海や山があり環境的に恵まれていること、その他、子育てのしやすい街であることなど、たくさんの魅力が語られた。
現状では東京に比べて仕事の予算規模が小さく、刺激も少ないものの「東京にいるよりもお金を使わないで生活できるため、『稼いで使う』というライフスタイルとは違う生活を楽しめる」(畠山氏)、「デメリットはメリットと紙一重。考え方をシフトしていくことで働き方や行動自体も変えていくことができる」(カズワタベ氏)、「東京にも安く行けるようになったので、福岡にないものは他の場所で補える」(下村氏)など、来場者がもっとも気になるであろう「仕事や生活への不安」についても現実的な意見や感覚とともに語ってくれた。
さらに、生活や仕事に関する具体的な質問が上がるなど、実際の体験にもとづく登壇者と来場者のコミュニケーションが印象的だった。

カズワタベ
国内のさまざま土地を転々とし、現在は福岡を拠点に生活するカズワタベ氏。新しいものに対する寛容な土地柄も福岡の特徴としてあげていた

畠山千春
福岡の糸島で暮らしている畠山氏。中心地から離れた田舎暮らしは、近所の付き合いも楽しく、現状にデメリットは何も感じていないとを語ってくれた

下村晋一
第1部登壇者のなかで唯一子どものいる下村氏は、パパ友ができるまでのプロセスを解説しながら「子育て」についての情報も提供した

毛利慶吾
昨年までWeb Designing編集部の編集者だった毛利氏。福岡に移住した人の知り合いがさらに福岡に移住する連鎖が起きている、という現状を語った

福岡のITコミュニティにくわしい特定非営利活動法人AIP(高度IT人材アカデミー) の村上純志氏(右)と、Web Designing編集長の馬場静樹(左)がファシリテーターを務めた

1時間半にわたり終始和やかな雰囲気で進んだ「住の部」。来場者にとっては移住経験者の生の声が聞ける貴重な時間となった
第2部 職の部 キーセッション&8企業プレゼンテーション
キーセッション01:池邉智洋氏_LINE Fukuoka(株)
キーセッション02:中村俊介氏_(株)しくみデザイン
![]()


池邉智洋
LINEで働くにあたってもっとも大事なマインドセットは、「エンドユーザーを愛してサービスを提供することに喜びを感じること」と述べた
![]()


中村俊介
しくみデザインはアーティストではなく、あくまでもクライアントがいるデザイナー集団であることを強く主張した中村氏。「東京は好きだけど、ちょっと疲れるなーと感じる人」は福岡で働くことに向いていると語った
第2部では、2つのキーセッションが行われた。前半は、LINEの取締役である池邉智洋氏が「LINE福岡拠点構想と求める人材」と題したセッションを行い、後半はしくみデザインの中村俊介氏が登壇した。
池邉氏は、LINEが福岡を「第2の拠点」として位置づけていること、国内だけでなく海外へのアクセスの利便性の高さや生活環境の豊かさといった点で選んだことを説明。今後は東京のフォローだけでなく独自に新サービスを発信していくことも語った。また、現在博多駅近くに建築中の新社屋について、さらには新規採用を続けるLINEが求める人物像を来場者に伝えた。
中村氏は、「インテル Perceptual Comp uting Challenge」でグランプリを受賞した、身体の動きに合わせて楽器のように音楽を奏でることができるアプリ「KAGURA」をプレゼン。その後、「みんなを笑顔にするしくみを作る」という同社の解説を行いながら、これまでの作品も紹介した。最後には、「コストの低い福岡で生活しながら、仕事は福岡以外から取ることもできる」など、中村氏なりの考えを教えてくれた。
福岡を代表する8社も参加


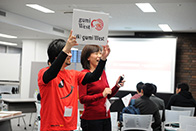



「職の部」では福岡を拠点に活躍の場を広げる8社のセッションも行われた。各企業の会社紹介が終わると「福岡に移住するとどんな仕事環境が待っているのか」「福岡で生活することの強み」など、仕事と生活に関する具体的な質問が投げかけられた。それらへの回答からは、福岡のコンパクトな土地柄、人と人の関わり方、会社同士の繋がりの強さという福岡ならではの特徴が伝わった。交流会では各企業のブース出展や個別企業説明会を実施。会社の所在地、採用人数、具体的な仕事内容、募集職種など、移住を見越したやりとりが各ブースで行われていた。
第3部 スペシャルトーク&交流会
スペシャルトーク:髙島宗一郎氏(福岡市長)、後藤玄利氏(ケンコーコム社長)
8企業出展&来場者との交流

後藤社長(左)と髙島市長(右)。創業特区として福岡市がどのような施策を行っていくかという来場者からの質問に、市長が熱心に答える姿が印象に残った
偶然にも、福岡が「国家戦略特区」の“創業特区”として選ばれたことが、イベント前日に全国ニュースとして報じられた。そのため、登壇した髙島市長は、特区としてどのような行政を進めるかを中心に語ることとなった。また、後藤氏は4月より本社機能を福岡市に移すことになった経緯などを解説。最大の理由として、福岡は「社員が暮らしやすい生活の豊かさがあり、活気がある場所」と語ってくれた。
なかでも、印象的だったのは市長による「かつては『左遷』という人もいた福岡が、魅力ある『移住』の地に変わってきている」という言葉だ。まるでこのイベントを総括するかのように、今の福岡にまつわる強い印象を残してくれた。
また、交流会で見受けられた、出展企業が詳しく会社説明を行う様子や、来場者が採用について真剣に耳を傾けている姿は、福岡への移住を生活面、仕事面の両面からサポートし、そのきっかけづくりを後押しする「ぼくらの福岡移住計画」が、参加者にとって有益なイベントだったことを物語っていたようにも見えた。
福岡市長からのコメント

福岡市が目指してきたのはアジアのリーダー都市です。それを実現するために3年続けてきたアクションが「国家戦略特区」として実を結ぶことになりました。東京にはない新しい価値を発信できる、チャレンジする人を応援できる場所としての福岡市。いまはその舞台作りをしながら、主役を演じるクリエイターのみなさんを募集しているところです。ぜひ福岡にお越し下さい、お待ちしております!

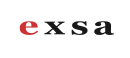 exsa(株)
exsa(株) 空気(株)
空気(株) (株)gumi West
(株)gumi West (株)サイバーコネクトツー
(株)サイバーコネクトツー (株)ヌーラボ
(株)ヌーラボ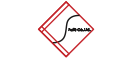 (株)Fusic
(株)Fusic (株)paperboy&co
(株)paperboy&co (株)ポリフォニーデジタル
(株)ポリフォニーデジタル